Vol.019 庄中一真さん
プロフィール:神奈川県在住。パソコン教室や中国料理店、医療系団体などの勤務を経たのち、縁あった寺院の宗派にて僧侶資格を取得。その後、所属宗派の本部に12年勤務し、現在はフリーランスとして、僧侶・執筆などの分野で活動中。僧侶としての専門は御祈祷。また国際中医師を目指し、本草薬膳学院の研究科にて現在勉強中。

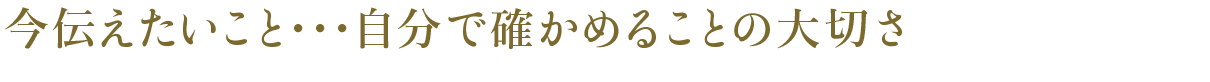
このたび「北京薬膳研修旅行」(2025年9月7日~12日)が8年ぶりに開催され、参加の機会を得ました。そこで感じた「自分で確かめることの大切さ」について書きたいと思います。
まずは中国料理について。「本場の中国料理は日本人の口に合わない」という言葉を何度も日本で耳にしましたが、本場の美味しい中国料理は日本人にも美味しいです。旅行中に訪問したお店はいずれも名店ばかりで、料理の種類や五味のバランス、見た目の美しさ、食材に適した調理法など、本場の凄さを感じました。また、どのお店でも冷水ではなく、常温以上の温度のお茶が提供され、胃腸を冷やさないように配慮されていました。
次に中医学・薬膳について。薬膳の土台は中医学です。今回訪れた北京中医薬大学にて「天人合一」という言葉を目にし、陰陽五行など中医学の土台となる考えや思想にも多く触れました。現代の西洋医学が病気や症状だけを診ることが多い中、中医学では宇宙・自然・環境・人などを一体のものとして観る思想があり、それを「天人合一」という言葉で表現しているのだと思います。
そのすべてを一体と観る思想によれば、体の病気や心の不調などは患部だけを診るのではなく、体全体もしくは家庭・生活環境をも観ていくことになります。それは繋がりを観る行為であり、繋がりから解決していく、とても理に適った素晴らしい方法です。
一方、解決までに時間や手間、高い経験値が必要となることは、経営的には非効率であるため、中医学・薬膳が普及する上での課題となっているのではないかと危惧します。
最後に、人の知識や経験には「自前」と「借り物」があります。自分で確かめ、実践することで「自前」が増えていきます。今回の北京薬膳研修旅行では多くのことを確認・経験することができ、「自前」を少し増やすことができました。この旅行でお世話になった多くの方々に心より感謝申し上げます。
 |